泊誌 著者 とまり会 昭和49年3月 発行
「南島風土記には、『あめくくち おやどまり なはどまり おやどまり』とおもろが引用されている。そのおもろにうたわれているあめくくちも泊のことを指していたとされている。また安里の一部泊寄りの所を脇泊と呼んでいたとも言われている。
以上のことで考えた時には、『とまり』はもともとは普通名詞であった。それが中山の玄関・貿易港としての発展で、人口が増えると共にこの普通名詞のとまりが固有名詞の泊村になった。」P6より引用
goo漢字辞典によると泊の意味として、 「①人が自宅以外のところにとまる。宿る。「宿泊」「外泊」 ②船がとまる。船をとめる。「停泊」 ③さっぱりしているさま。「淡泊」」となっている。https://dictionary.goo.ne.jp/word/kanji/%E6%B3%8A/
Wikipediaでは「泊(とまり)は、古語で船を停泊させる水域のこと。湊・港は類義語。津は主に渡河船の船着場を指す。転じて宿泊の意味としても用いる。」としている。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%8A
中山王朝以降の港としての役割を持った土地を普通名詞として「とまり」と呼んでいた場所が、固有名詞としての地名「泊」になったと思われる。つまり、琉球王朝の港と言えば「泊」であり、国の機能としての「港」と港や船を運用する「役人・士族」が住む土地としての泊村があって、そこに住まう士族の武芸の一つ、嗜みとして「泊手」を使う「武士」が泊村にはいたのだと推測します。
泊誌には泊の発祥や歴史、文化について500頁あまりの内容になっていて、その中には「空手(泊手)中興の祖松茂良興昨略伝」についても掲載がある。その他、泊バーリーの逸話や綱引き、史跡や名勝、琉歌に見る泊、廃藩と泊村共有財産護持運動など色々な読みどころはありますが、まだまだ読めておらず今後勉強していく予定です。
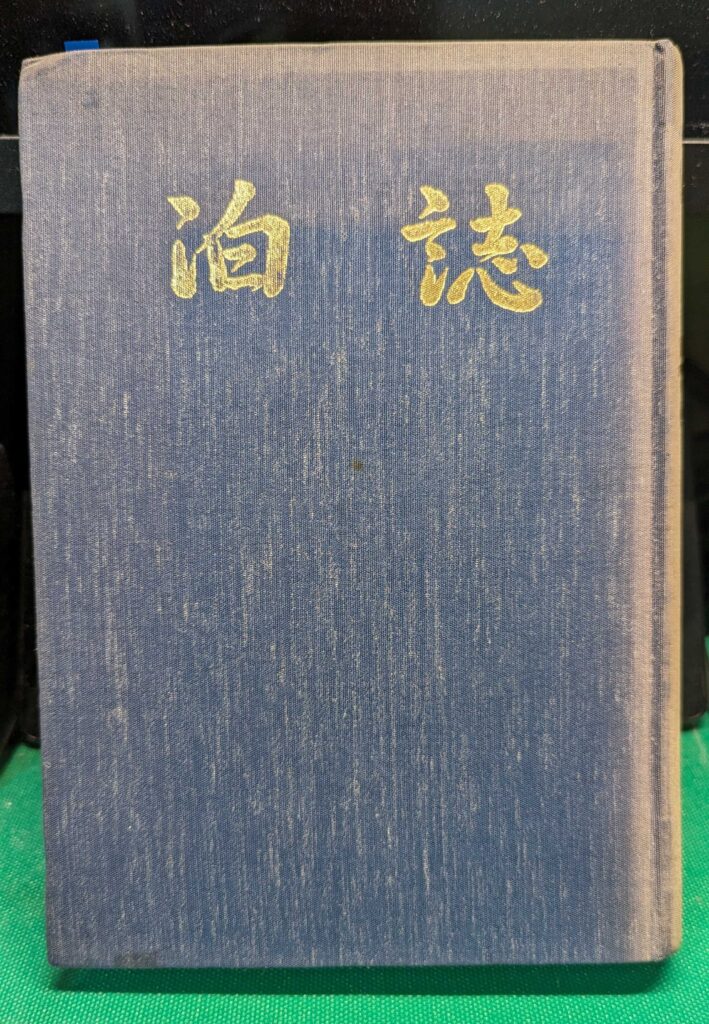
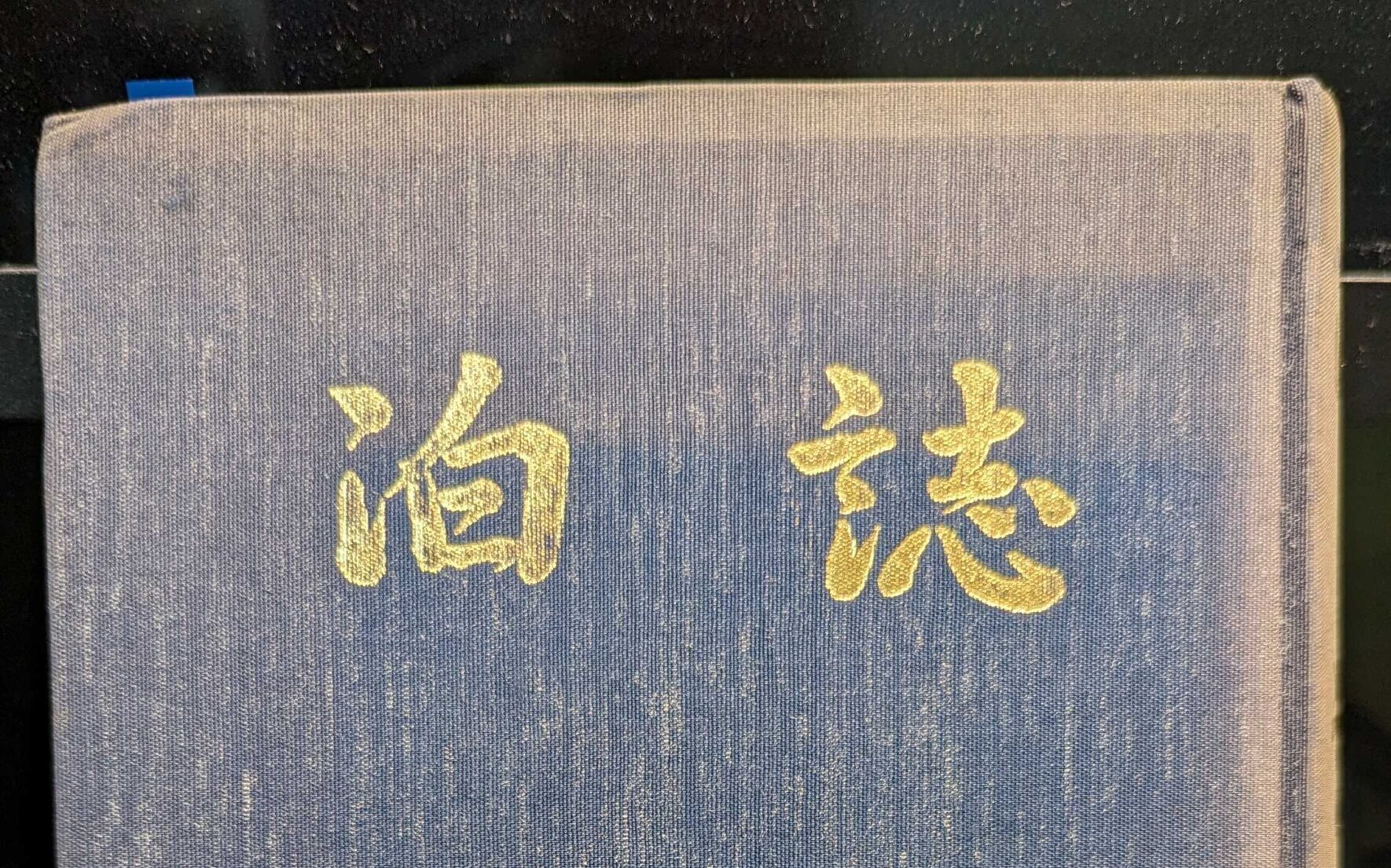


コメント